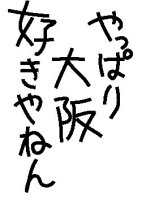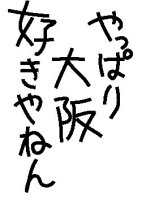|
私は3人きょうだいの末っ子。いとこの中でも最も年下やったから、幼いころから、祖父母にも、両親にも、年の離れた兄たちにも、そして親類縁者にも、それはそれは、かわいがられて育ってんよ。お菓子やおもちゃを分けるときも、初めにもらえるのはいっつも私。まるでお姫さまのような暮らしやったわぁ。
けど、仏様はさすがに人を平等につくってはります。たった1つ、末っ子ならではの大きな悩みがあったんです。
それは、服や持ち物に"おふる"が多いことでした。お蔭で、たいそう衣装持ちやったことは確かですけど、あるときは豪華なフリルの付いた、どうがんばっても私には似合うはずのないワンピースを着せられたり、あるときは男もんの青いシャツやったり…。とてもやないけど、自分の趣味を主張する余地はありませんでした。
おふるの筆頭は、私が1年生になったときにもろたリュックサックでした。いとこたちが、すでに5代にわたって使い回した、10数年の"ビンテージもの"やったと思います。
初めての遠足。真新しいリュックを背負った同級生たちの後ろ姿は、色とりどりに咲き乱れたお花畑のようでした。ところが私のは、元は赤かったんか白かったんか、もはや判別もつかんような微妙(?)な色合い。「けったいなカバンやなぁ〜」。みんなから散々くさされて、なんと肩身の狭いこと。
けど私はその時、ある決心をしたんです。日本経済の発展が著しく、浪費が豊かさの証しであるかのように思われ始めた時代でした。「どんなものにも命がある」と、いつも両親から聞かされていた私は、あえて時代に逆行して、そのリュックの命が果てるまで、徹底的にお世話になってみようと思たんです。
それから数年後、確か小学4年生の頃やったと思います。秋の遠足の帰り道、背後で何やらパラパラ落ちる音がするので見ると、愛用のリュックの底がすっかり擦り切れて、大きな穴があいてたんです。帰宅して母に修繕を頼むと、母は真直ぐ私の目を見て言いました。「いつ新しいのが欲しいて言い出すかと思てたけど、ようここまで大切に使ぅたね。もう修理はせんでええから、今度、さらを買いに行こ」。
遠足を間近に控えたある日曜日、母は朝早くから、私を梅田の百貨店に連れて行ってくれました。けど、私の気に入るデザインのものはなかなか見つかりません。それでも母は、私のわがままを叱るどころか、私がうんと言うまで、大阪市内の百貨店やカバン屋さんを、丸1日かけて駆けずり回ってくれたんです。
さて当日。みんながちょっとくたびれたリュックを持つ中で、たった1人、お洒落な新品を携えた私が、羨望の的になったことは言うまでもありません。その日の私の誇らしげなおみやげ話を、母は目を細め、ほんまに嬉しそうに聞いてくれました。
…で、その新しいリュックは、その後どうなったかて?
年下のいとこはいてなかったし、今さら次世代に引き継ぐには骨董品すぎるしね。けどご心配なく。実は今なお、それは私の宝ものやねん。あの恐ろしい阪神・淡路大震災以降、立派な「緊急避難用品袋」に生まれ変わって、私をそっと見守ってくれてるんですよ。
|