| 【第8回】 《第2章 走りだした大阪コレクション》 |
| ■試行錯誤の連続 |
| 昭和62年7月15日の「大阪コレクション開催委員会」設立総会で運営組織、事業内容、事業予算などの承認を得たわれわれスタッフは、同年11月25日から3日間の本番に向けていよいよ本格的な準備作業に突入する。 とは言っても、やはり素人集団、試行錯誤の連続だった。それと当時の大阪が、いかにファッションに縁遠い街であるかを随所で見せつけられる。いくつかのエピソードを記憶のままに記しておきたい。 |
| ■女性委員が少ない? |
| 時間は少々さかのぼる。6月9日、われわれは設立総会に向けた最終打ち合せを行い、実行委員候補を決定した。だがその候補者リストを見た佐治敬三大阪商工会議所会頭(サントリー社長)から注文がついた。 「ファッション事業をやろうというのに、メンバーを見ると、コシノさん以外は、がさつな男ばかりやないか。ファッションのわかる女性に入ってもらわんでええんか?」 ごもっともである。だが、当時の大阪では、第一線で活躍する女性は本当にわずかであった。佐治さんから意を託された柴田暁サントリー秘書部長と私は、即座に「湯浅(叡子・千里文化財団専務理事)さんにお願いする」ことで一致した。佐治さんの了解を取った上で、私が湯浅さんをお訪ねし、承諾を得る。 だが、できたらもう1人女性委員が欲しい。そこで「事務局は引き受けられないが、協力はする」というトータルファッション協会に知恵を借りる。すでに実行委員とは別に編成する選考委員会の委員候補に選ばれていたアパレルメーカー・ラピーヌの江村美代子代表取締役専務(当時)に実行委員との兼務をお願いした。 |
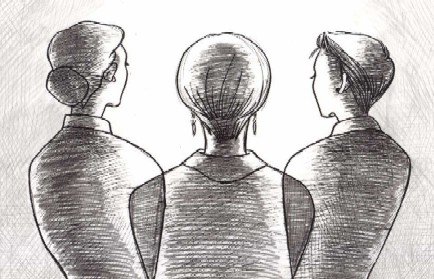 (イラスト: Yurie Okada, ROGO Ltd.) |
| こうしてコシノさんを加え、3人の女性実行委員を選任することが出来たのだが、当時の大阪は、有能な女性を抱えながら、女性起用を怠っていた。関西経済同友会がこの3氏をはじめ、会員に女性を多数起用、会の雰囲気と活動内容を一変させるのは、同コレクションの推進メンバーの一人である萩尾千里さんが常任幹事・事務局長に就任してからのことである。近年でこそ、同会を活動拠点にした女性リーダーの活躍が多方面で目立つが、10数年前といえばこんな感じであった。 |
| ■スタッフ不足 |
| また、ファッションショーを舞台裏で支える人材も大阪にはほとんど育っていなかった。「大阪コレクション」の立ち上げを決めたとき、われわれには「この事業は、若手のデザイナー発掘のほか、グラフィックデザイナーや、モデルをはじめファッションショーに関係するあらゆる人材にチャンスを提供する場にしたい」という思いがあった。 そこで、プロデュースを依頼した博報堂の堀川紀年氏にその旨をお願いしていた。だが、「極力その方向で努力します」とは言ってくれたものの、この分野での大阪の人材不足は深刻だった。ポスターなどのグラフィック関連は、当時大阪を拠点に活動していた黒田征太郎氏に依頼したものの、他の部門はほとんどを東京スタッフに頼らざるを得なかった。 ファッションショーを成立させるには、素人の想像以上に多くのスタッフが必要だった。ショーを演出するディレクターから始まってスタイリスト、ヘア・メークアップアーチスト、モデル、照明、音響、舞台装置、それぞれのアシスタントを入れると総勢100人を超える人数になる。質、量ともに当時の大阪にはそれだけの人材はいなかった。 結局は5年前に開催した南御堂でのコシノ3姉妹ジョイントショーの時と何ら変わらぬ状況だった。つまりはわずか1回きりのお祭りを仕掛けても、実態は何ら変わらない。継続しなければ力にならぬことを痛感させられた。こうして、とにもかくにも総合プロデュースを博報堂と、3姉妹ジョイントショーでお願いした東京のサンデザイン研究所(大出一博社長)に依頼、乗り切ることになる。 |
| ■出品デザイナーの選考 |
| こうしたことの他に、決定的に大阪の力不足を痛感したのは、ファッションに関するステータスの差であった。それは出品デザイナーを審査する選考委員会の編成に端的に表れていた。 「選考委員会の権威が、大阪コレクションの権威を決定する。全国的に認知してもらうためには、全国的に認知される委員を委嘱しなければならない」という考えから、地元委員に加えて東京から大出氏のほかファッション評論家の大内順子さん、東京ファッションデザイナー協議会の太田伸之議長(当時)、ファッション雑誌『ハイファッション』の久田尚子編集長(当時)の4氏に加わってもらう。こうして万全の選考体制が整った。 選考は厳しく行われた。「出品デザイナーの実力が大阪コレクションの格付けを決めてしまう」という判断からだった。 |
 第5回(91年)平戸鉄信さんの作品 |
| 20名近い自薦、他薦のデザイナーが応募してきた。出品枠は6人だが、うち1人は開催委員会推薦としてコシノヒロコさんが決まっていた。残る5人を選ぶのが選考委員会の仕事だったが、結局、4人の選考で打ち切っている。選ばれたのは繁田勇、平戸鉄信、古川雲雪、山中緑の各デザイナーたちだった。そして、もう一枠は関西出身で、東京コレクションのメンバーとして活躍していた細川伸さんに開催委員会推薦としての出品を要請、何とか6名の人数を整える。 「若い、才能あるファッションデザイナーが関西でもたくさん活躍している」というものの、残念ながら当時の状況はこんなものであった。しかも、山中緑さんが当時31歳の文字通り若手デザイナーであったほかは、繁田、平戸、古川各氏とも40代、50代のその世界では中堅からベテランに属するデザイナーであった。そういう実績あるデザイナーでありながら、大阪のほとんどの人がその存在を知らなかった。 灯台もと暗し、とはいうが、「繊維の街、大阪」といわれながら、ほんのごく一部の関係者以外、デザイナーに関心を寄せる人はいなかったのだ。もちろん、かく言う私もまた、そうした大阪人の一人だった。 |
| ■カルチャー・ギャップ |
| 出品デザイナーも決まり、諸々の計画の委員会承認も得て、いよいよ舞台作りが始まった。そこで私が最も印象的だったのは、新たな出会いをしたファッション界の人たちとの感性の違いだった。それまでの私の世界は、経済界や行政あるいは学界に関わる方々との交流が中心であり、ファッション界といえばコシノさんとの付き合いがあるだけ。5年前の御堂筋フェア'82の時には、制作部門にはほとんどタッチしていなかったから、クリエーターとの膝詰めの付き合いは、これが事実上初めてだった。 口髭を蓄えた繁田さんの風貌はチャップリンそっくり。頭髪をカットしたことがないという古川さんの髪の毛は地面に届きそうな長さで、ヒッピー生活の体験者という。平戸さんの感性もソフトで、われわれとは違う一種独特のものがあった。最若年で、むしろおどおどしながらわれわれに語りかけてきた山中さんが、なんとなくわれわれに近い存在に見受けられたが、身に付けるもの、発言の内容や言動などどれを取っても、われわれとは違っていた。 しかし今になって考えると、最初に出会った彼らの感覚は、少なくとも世代が近いだけに、まだまだ理解できるものがあった。後々になって登場する超若手のデザイナーたちとなると、まるっきり異人種的存在であり、そのギャップにしばしば困惑することになる。だが楽しみもそれだけ大きかった。 モデルのオーディションにも、事務局として立ち会ってもらいたいということで、その年以来毎回立ち会っているが、小柄な私にすれば、175cm前後のモデル嬢の中に巻き込まれると、すっぽり埋まる感じで、できる限り彼女らの群れから遠く離れて待機するようにしていた。よくもこんなに大きな女性が多いものかと感心したりしたものだ。 |
 左から、繁田勇さん、古川雲雪さん、平戸鉄信さん、山中緑さん |
| ■ハイビジョンの実験放送 |
| そんな折、NHKから興味ある企画が飛び込んできた。2000年12月から本格放送が開始されたBSハイビジョンの実験放送を「大阪コレクション」で試みたいという依頼である。もちろんそれに伴う費用の一切はNHKが負担するというのだから、われわれとしては快くその場を提供することにした。 ハイビジョンの特色は、画面を作っている走査線が1125本(通常のテレビは525本)で、それが大阪コレクションの本番初日である「11月25日」に一致することから、語呂合わせでこのイベントが採用されたらしい。ハイビジョンの実験放送はそれまで、放送センターで収録、再編集して放映されており、放送衛星を使って生中継するのは世界で初めてということだった。 当日、会場となったマイドームおおさかで収録された映像は、放送衛星を通じて隣接する大阪コクサイホテルに設置された大型のハイビジョンテレビに送られ映し出されたが、その鮮明さが記憶に残っている。映像は世界初のハイビジョン生中継映像としてNHKに保存されているだろうが、幸先良いスタートを切らせてもらったことになる。 |
| ■メニエル症候群で英雄に |
| 制作のほとんどは博報堂の堀川紀年さん、長尾忠之さん、それと大出一博さん率いるサンデザインの皆さんが担当してくれたが、やはり要所要所では引っ張り出される。その他私には、サントリーの柴田暁さんと組んだ資金集め、スポンサー団体の大阪府・市、大阪商工会議所、大阪21世紀協会との折衝ごとの仕事がある。それにもまして『関西ジャーナル』の発行という本来の仕事があった。40代前半の、体力には自信のあった私だったが、多少、心労があったのだろう。 私事で恐縮だが、閑話一題。 11月24日、その日はすべての準備を終え、佐治敬三委員会会長とデザイナーが参加する記者会見を予定していた。裏方に徹する私にとっては、司会役のその日が唯一の晴れの舞台である。その朝も、いつものように出勤の準備をし、いざ出陣と立ち上がった途端、眩暈に襲われ、天井はグルグル、歩けばヨロヨロ、そのまま床にひれ伏してしまう。回復を待つが、一向によくならず、30分待ってついに万事窮す。這うように電話器まで辿りつき、会社に連絡を入れる。 「昼まで待てば、回復すると思うが、最悪、記者会見に間に合わないかもしれない。その時は、大谷吉弘さん(大商の担当課長)に記者会見の司会をお願いしてほしい」 結局、午後3時からの記者会見に出ることはできなかった。大谷さんにはそれ以後、何度も「あの時はまいりましたよ」と、責められる(?)羽目になる。 夕刻になって、なんとか立ち上がれるようになり病院に向かう。「メニエルだな」と医師。「軽い症候群だから、明日1日寝ていれば治るよ」とのこと。だが明日は本番。寝ているわけにはいかず、翌日、まだ血の気のない顔をして本番会場に。 驚いたことに、「折目、倒れる」の情報は仲間内に一巡していたらしく、口々に優しい言葉(?)の雨嵐。「俺たちでやるから、君はそこに座って見ているだけでいい」と、初めて接する慰労の数々、すっかり英雄に祭り上げられていた。 |
 |
| ■第1回大阪コレクション |
| こんなあんなで、いよいよ11月25日から3日間にわたる第1回大阪コレクションは開幕する。例によってその模様は、同年12月1日号の『関西ジャーナル』の私の記事で再現した。 「大阪をファッション情報の発信基地に」の期待を込めた第1回大阪コレクションが11月25日から27日までの3日間、大阪・内本町のマイドームおおさかで開催され、約7300人が、6人のデザイナーが披露する最新のファッションに陶酔した。 (中略)"繊維の町"大阪として、繊維産業の隆盛を築いた大阪だが、素材偏重の咎めか、ファッション化に立ち遅れ、「大阪には実力のあるデザイナーが育っても、その作品を発表する場がない」(コシノヒロコさん)ほどの低迷振り。(中略) そこで「この状況を作ったのは、他でもない大阪人の責任であり、大阪文化の欠陥と自覚せねばならない」(佐治大商会頭)と、行政と経済界が一体となって、世界的なデザイナーを送り出す舞台づくりに乗り出すことになったもの。(中略) 大阪で開かれる初めてのコレクションとあって、入場者も主催者の当初予想(5000)を大幅に上回る7300人にのぼり、とりわけフィナーレを飾ったコシノさんのステージは、1回で収容できず、急遽2回にわけるほどの盛況ぶりだった。(中略) (文中の敬称はいずれも当時) |
| 『千里眼』No.73(2001年3月25日)掲載 |
|
|