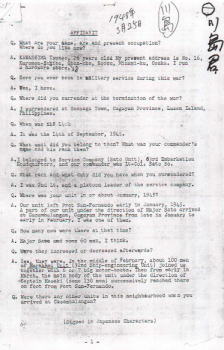|
| |||||||||||
| |||||||||||
|
| |||||||||||
「光陰矢の如し」と申しますが、ふと立ち止まると、齢すでに80歳。随分色々なことがありましたが、最も印象深いのが、あの第2次世界世界大戦に参加したことです。そして、戦後の混乱期から今日まで、ただただ、がむしゃらに働き続けて来ました。 平和と豊かさが当り前のように感じられる今日の社会にあって、50年余前、自ら戦争を体験した私にとって、その「勝」や「敗」にかかわらず、戦争が如何に悲惨なものであったかということを、ぜひ記録に残しておかねならぬとの思いから、私の経験の一部を拙文にいたしました。 「お国のため、君のために生命を惜しまず戦うことが男子の本懐だ」と叩き込まれ、戦場にかりだされた私を、父母兄弟は心ならずも「頑張って働いて来い」と言って見送りました。しかしその本心は「必ず無事に帰って来て欲しい」であり、私自身も、生命大事と思い続けていました。 その父母の切なる願いにも拘らず、一歳違いの弟が昭和20年1月14日、台湾沖の海戦で「特攻隊」に組み込まれて戦死しました。「名誉の戦死」との一片の紙切が届いただけでありました。 人間同志が全力を出して殺し合うということほど馬鹿げて残酷な、悲惨なことがあるでしょうか。どんな事情があるにせよ、戦争は絶対避けねばなりません。強い軍事力も必要でしょうが、外交による調和を最優先すべきです。万一、再び戦争が起これば、今度は瞬時に国も国民も滅んでしまうでしょう。これが老人の戯言であれば幸いです。 |
|||||||||||
| 平成14年1月 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| 轟沈…前途多難な出陣 ― 夕暮れの出港 行先は、ただ“南方” ― | |||||||||||
| 昭和19年10月20日、我々兵員を満載した13隻の輸送船団は、やや陽の傾いた広島の宇品(うじな)港を、岸壁からの見送りもなく密かに出港した。行き先は我々にも秘密にされていた(支給された服装により、南方であろうと想像できた)。日向灘を通り、陸地が見えなくなった頃、次第に日が暮れて来た。 その頃、既に日本近海にも危険が及びつつあった。敵潜水艦の襲撃を警戒して、前後左右に大きく広がった船団は、一切の灯を消して黙々と波を蹴っていた。そろそろ皆が眠りに就く頃、右遠くの船に真っ赤な火の手が上がり、続いて雷のような爆発音が聞こえた。「潜水艦だぞー。魚雷だぞー。配置につけ!」の大声と共に、各船から一斉に「ボー、ボー」という汽笛が鳴った。早くも敵潜水艦の襲撃である。
船上は急にざわめいた。暗闇の中に紅蓮の炎を上げているのは油槽船(ゆそうせん)だと分かった。甲板には、炎の中を右往左往するゴマ粒のような人影が見える。それでも、その船は速度を落とさずに走り続けた。海上のことなので助けようがない。20分も経ったと思う頃、再び爆発音が轟いて、四方に飛び散ったその船は、忽ち見えなくなってしまった。 暗闇の中の船団は、何事もなかったかのようにそのまま走り続けた。 あの船の人々はどうなっただろうか、ということが一瞬、頭をかすめたが、急に敵地に入って来た私には、それ以上の余裕はなかった。白く光る航跡は、スクリューの渦に刺激された夜光虫の光であって、いつまでも長く尾を引いていた。それが、敵の大きな目標になるのだ。それでも船団は黙々と南下を続けている。 夜の暗闇とは人々を一層不安にするものだ。全員が、寝られぬままに甲板に出て、海上をぼんやりと眺めているだけである。やがてやっと重苦しい夜が明けて来る。やれやれと胸を撫でおろし、顔を見合わせる。でも船団は案外静かな海面をひたすら進んでいる。 敵潜水艦が再び現れないことを祈りつつ、不安な日々が10日程続いた。ふと気がつけば、なんと船団は東に向かっている。時には北々西の時もある。聞けば無線の指示により、「敵潜水艦群を回避して」との事であった。行きつ戻りつ、一体いつになったら目的地へ辿り着くのやら。海面のほか何も見えない。 そして11月6日の朝がやってきた。どうやら昨夜も無事だった。 後日知ったことだが、この時の我々船団の位置は、バシー海峡のど真ん中辺りであり、フィリピン海溝と呼ばれる、水深7000m以上の巨大な海底の裂け目の真上であった。 |
|||||||||||
|
| |||||||||||
| 潜水艦群を前に、手も足も出せない船団 | |||||||||||
朝だ。皆の疲れた顔にも生気が戻った。 「点呼」、「宮城遥拝」(天皇陛下の居城を遥か遠くから礼拝すること)の声と共に、船上は急に活気づいた。「飯上げー」(食事の分配をするので炊事場へ取りに来いという合図)、「番号」など、聞き慣れた声が、夜の長い緊張と重苦しい暗い気持から、我々を平常心に引き戻した。11月6日の朝7時であった。 しかしそれは、ほんの僅かの間であった。 敵の飛行機が1機、どこからともなくやって来て、船団の上を何度か旋回して飛び去った。皆の顔に不安の色が走った。すぐまた1機が現れて、ゆうゆうと頭上を旋回し、最後に、後ろの船に爆弾を1個だけ落として飛び去った。間もなくその嫌な予感が的中した。まだ見えないが、敵潜水艦の包囲網が忍び寄っていたのだった。 「右前方潜水艦!」。見張り員の甲高い声に、皆の目が一斉にその方向の水面に集まった。大きなうねりの間から、白い尾を引いた魚雷が2本、猛スピードでこちらに向って来るではないか。全力で舵を取る船体が、船尾をじわりじわりと左へ振るのがじれったかった。それでも無事船尾すれすれに、魚雷は通り過ぎた。 思わず「万歳!」と叫んだ。しかし不運にも、魚雷は左後ろを走っていた船に命中した。轟音と共に、前半分をもぎ取られた船は、全く走る力を失った。その後、続いてあちこちに爆発音が轟ろいた。我々船団は完全に敵に包囲されたのだ。 「駆潜艇」と呼ばれる小さな護衛船3隻が、忙しく海面を走り回って、爆雷(水中深くまで沈めて爆発させる、対潜水艦の兵器)を落としているが、大した威力もないのか、潜水艦は四方から攻撃を加えて来る。船上の高射砲が、敵の潜望鏡を狙ってドカンドカンと発射しているが、勿論私たちには手も足も出せない。 |
|||||||||||
|
| |||||||||||
| 漂流…太平洋をただ独り ― 魚雷命中、決死のダイビング ― |
|||||||||||
| 轟沈(ごうちん=爆発と同時に沈むこと)する船がある。大きく傾いた船が動けなくなっている。無数の兵員がその船にしがみつき、あるいは海上に浮いている。「ズシーン」。瞬間、体が空中に放り上げられた。「やられた!」と直感した。私の乗った船の汽笛が「ボー、ボー、ボー」と鳴った。退船命令だ。この船には爆雷が満載してあったのだ。これに火が回ればひとたまりもない。轟沈間違いなし。 「これまで!」と覚悟を決め、救命胴衣を着けて海に飛び込んだ。勿論、軍服を着たままだ。他の兵員たちも後から後から飛び込んで来る。高いうねりが容赦なく我々に襲いかかる。傾いた我々の船は、暫くは火焔に包まれて浮いていたが、遂に大きな爆発音と共に真っ二つに割れて、アッというまに沈んで行く。みるみる水面は、救命筏とそれに取りすがった人々で一杯になった。 誰からともなく軍歌の合唱が始まった。 ♪吉野を出でて打ち向う 飯盛山の松風に 靡くは敵の白旗か 響くは敵の鬨の声・・・ 冷たい水に浮いた私は、妙に落ち着いてきた。同僚の顔が皆、泣き笑いしているようだ。波を被りながら、
まだ、爆雷の音は続いている。その衝撃波が、海上に浮んでいる我々の腹をズシンズシンと叩く。体がやけに冷たくなってきた。暫く続いた軍歌も、いつしか聞えなくなっていた。ただ疲労と挫折感が我々を支配した。 暫くすると、潜水艦が大きな顔をして浮上し、水面の我々に機銃の雨を降らせて来た。ただ、大波に揺られている我々にとっては、あまり恐ろしい気はしなかった。 |
|||||||||||
|
| |||||||||||
| 夢うつつの波の上 | |||||||||||
| やがて潜水艦が去ったのか、海面が静かになった。うねりが大きいので、高く上がったときは随分遠くまで人々が浮いているのが見える。また、低くなったときは、谷底にいるようだ。 2、3時間も経っただろうか、日の丸をつけた双発の飛行機が2機、水面近くを飛んで、翼を左右に大きく振った。涙が出るほど嬉しかった。が、その飛行機に守られて、沈みかけた船、動けない船、そして水上を漂う我々を残して、無傷の船は去って行った。 護衛艦だけが、懸命に救助を続けている。見る見る艦は人で鈴なりになった。そして、積み残した我々に「許せよ、頑張れよ……」と点滅信号を送って艦は走り去った。波はますます大きくなり、速い海流にも流されて、水面に浮いていた我々の筏も、だんだん散らばって行った。
潮流のせいで、足先が妙に暖かくなったり冷たくなったりした。それは海水の色ででもはっきり区別ができた。帯状になって流れる暖流の存在を、はっきりと意識した。 ふと気がつくと、筏の周りには5、6人しかいなかった。1人は両手に火傷をして苦しんでいたので、筏の上に押し上げてやった。水が欲しいと言うので、水筒を与えた。うまそうに飲み干すと、急にぐったりした。手の皮が、手袋を脱ぐように分厚くめくれて、血が吹き出してきた。間もなくその男は筏に横たわり、次の大きな波に呑まれて行った。我々はそれを引き止める力もなかった。 3時間も経った頃には、私が掴まっていた筏も、波に揉まれてバラバラになってきた。そして遂に、周りには誰もいなくなった。海上に浮かぶ粟一粒だ。それと前後して、沈んだ船から色々なものが次々に浮き上って来た。私は運よく、目の前に勢いよく浮び上って来た長さ5m位の丸太に掴まることができた。しかし、最早なす術もなく、ただただ水面を漂っているだけである。大きい波は、容赦なく頭の上から襲いかかる。耳から入った海水が、鼻や口へ自由に抜ける。それを防ぐ力も残っていなかった。 そのまま時間が過ぎてゆく。ガンガン照り付けていた太陽も、大分西に傾いて来た。 その頃、私の体力は既に限界を越えていたのだろう。万国旗を掲げた美しい船が何隻も見えたり、松林のある海岸がすぐ前に近づいたり、静かな座敷でくつろいでいるなど、妙な夢や幻のようなものを見ていたように思う。 諦めて、何度も水中に頭を突っ込んで死のうとしたが、その度に、父母の顔が現れて「死んではいけない。まだせねばならならぬことがある」と呼び掛け、私を勇気づけてくれたようだった。 |
|||||||||||
|
| |||||||||||
| 三十六時間後・・・・ | |||||||||||
ふと気がつくと、もう真っ暗だった。随分経ったようだ。気絶していたのか、その間は全く覚えがない。よく丸太を放さなかったものだ。冷たい雨が降っていたので、それで気がついたのかも知れない。そして、また気が遠くなり、何も分からなくなってしまった。 無意識のまま、丸太だけは放さず、私はただ独りで漂流物のように流されていたのだろう。照り付ける太陽も、頭から襲いかかる波も、私の無意識が救ってくれたのだろう。 突然「おーい」と呼ぶ声に、気がついた。目の前に大きな駆逐艦が止まっているではないか。しかも、何人かの水兵が大声で呼んでいる。ぼんやりとした頭には、これが幻なのか現実なのか、すぐには区別がつかなかった。 しかし、すぐにロープが投げられた。ところが私には、それに掴まって上がる力が残っていなかった。すると今度は、ロープを輪にして投げてくれ、「両腕を通せ」と怒鳴る声が聞こえた。 私は、釣り上げられたマグロのように、船に引き揚げられ、ドサリと甲板に投げ出された。先に助けられたと思われる数名が、同様に無造作に横たえられていた。船は全速力で走り出した。潜水艦のウヨウヨする海域だったのか、助けられたのは私が最後だった。午後6時過ぎだったと思う。 駆逐艦の全速航行中は、魚雷も艦の走行の水圧に押し戻されて、艦底を抜けるか、横波に蹴飛ばされるとのことであった。 何時間かそのままでいるうちに、少しずつ意識がはっきりしてきた。でも、目と頭以外は全く働かず、首から下は、存在さえ分からなかった。ただ横たわることしかできなかった私は、少し頭を動かして、段々近づく陸地をじっと眺めていた。 船から海に飛び込んだのは、昭和19年11月6日の丁度午前7時であった。そして、その日1日と、翌日の午後6時過ぎに救助されるまで約36時間、太平洋を漂流していたことになる。 我々の船には、出港時、3000人の将兵が詰め込まれていたが、助かったのは総数250人であったとのことである。 そして、その後の陸上での戦いでも、大消耗戦が展開されることになる。 |
|||||||||||
|
| |||||||||||
| 苦戦また苦戦…ルソン島地上戦 | |||||||||||
駆逐艦から上陸したのは、フィリピン・ルソン島西海岸の「ガブガオ」というところで、19年11月8日の夕方であった。丸1日休養をとった私は、一緒に救助された数人の将兵とともにマニラへ赴き、そこで再編成を受けた。 その日から、マラリア、デング熱、その他の悪疫に悩まされつつ、転進また転進の苦しい戦いが続くのである。補給、補充のない戦は、万に一つの勝ち目もなく、自然消滅の運命である。 昭和19年の暮になると、既に制空権はアメリカ軍の手中にあり、マニラも毎日何度となく空襲を受けていた。我々が再編成を受けたのは、マニラ北方 200kmの、リンガエン湾に面するサンフェルナンド港にある船舶司令部の増強部隊としてであった。私(指揮官)以下、約30名は、12月15日、同港に着任した。司令官以下、約250人の規模であった。第六十三碇泊場指令部と呼ぶ。 12月27日夜、私は、部下20数名を率い、先遣隊として漁船3隻でルソン島北部の「アパリ港」(直線距離で約 300km)へ前進の命令を受け、出航した。それと入れ違いに、翌28日、早速司令部の前に、アメリカ大艦隊が侵入して来た。その艦砲射撃の激しさは、空襲どころではなく、地表が全部掘り起されたようであったとのことであった。しかし、既に航海中の我々には、砲声が遠く近く、後方に聞こえる程度であった。 しかし3日間の航行の後、漁船は敵機の激しい銃撃で破壊され、残る 150kmは徒歩であった。難行軍の末、やっと到着したのは、20年1月20日であった。
そのアパリ港も、敵の来襲によって間もなく破壊され、遂に我々は50kmの移動を余儀なくされた。そして、ルソン島東北端の「パトリナオ」で、ジャングルの中に身を潜めながら、陸戦によるゲリラ戦を繰り返した(このとき、私は陸軍少尉に任官していた)。しかし、食糧・弾薬・医療品も全くない悪条件により、マラリア・デング熱・栄養失調で死亡する者が続出、惨澹たるものであった。この苦戦は、20年9月上旬まで続いた。 そこで、このままで手をこまねいて全滅を待つよりはと、残存総力を挙げて「突撃斬り込み」を敢行すべく準備をしていた。しかし実は、約1ヵ月前の昭和20年8月15日に、既に戦いは終わっていた。 そして我々は、突撃敢行直前の9月14日に届いた軍命令により、陣地を離れ、武器を棄てたのである。 |
|||||||||||
| (詳細は、別記『私の軍歴』の項を参照下さい) | |||||||||||
|
| |||||||||||
| 海底に消えた貴重な若き人材・物資 | |||||||||||
| 広島の宇品港から出港した船団13隻のうち、5隻だけが無事フィリピンに着いたことを、後で知った。私の乗った輸送船「大洋丸」(3000トン)は轟沈し、兵員3000名のうち救助されたのは約 250名であった。
武器・兵器満載の船団は、大部分が馬匹もろとも深さ7000mの日本海溝の底へ消えた。長引く戦争による物資欠乏の中にあって、日本中が総力を挙げて集めた貴重な物資・兵器・馬匹、その上に若い男子の大部分も、一瞬の間に失われたのである。 私は、終戦と共に米軍の捕虜となったが、そこにはまた苦しい日々が待っていた。即ち「戦争犯罪人」としての半年に余る、日々の取調べであった。その間、他の部隊の幹部たちは理不尽な裁判で次々と断罪を受け、処刑されていった。 勝てば官軍、一方的な裁判には道理も何もあったものではなかった。そんな厳しい法廷にあっても、我が部隊司令官、佐藤操氏(平成4年10月死去)は最後まで諦めず、捨身の反論と信念をもって争い、遂に我々に無罪を勝ち取ってくれた。これは私にとっては、何ものにも代えられない誇りであり、大恩である。 戦いで文字通り九死に一生を得、また裁判でも無罪を勝ち取ることができた私たちは、今こうして平和に暮らせることを心から感謝している。我々生き残った戦友も、戦後50余年を経て、年々一人、また一人と鬼籍に入りつつあるが、命ある限り戦争の犠牲者の慰霊を続けるのが使命だと感じている。 そして、二度と不幸な戦争が起こらないことを切に願っている。 |
|||||||||||
|
| |||||||||||
|
|||||||||||
|
| |||||||||||
|
|||||||||||