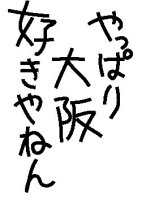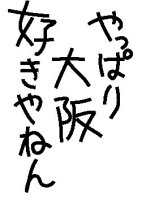|
私の家族は歌が得意。母は女学校のときから謡曲で鍛えた本格派やし、兄たちは、コーラスやバンドで女の子らにキャアキャア騒がれるほど、子どものころからセクシーボイスの持ち主でした。
そやのに、なぜか私だけは物心ついたころから妙に低音で、しかもダミ声。精一杯すまして友だちに電話しても、取り次いでくれる家の人はたいがい「小山君から電話やで〜」。けど、男の子に間違われるのは、まだマシな方でした。「風邪引いたん?
そないに声からして」と真顔で尋ねられたら、返す言葉もあれへんかったわぁ、ほんま。
小学校のコーラス大会で、私はピアノ伴奏の大役を仰せつかりました。特にピアノが上手やったからとちゃうんですよ。音楽の先生が、練習中に私の呻くような声を、ちょけてると勘違いして「あんたは音楽に合わせて口だけパクパクしとき!」と叱りはりました。けど、私の泣き出しそうな顔を見て、それが地声やったと悟った先生は、私が多少ピアノを弾けたため、伴奏の特訓をしてくださったというのが真相でした。
そんな惨めな舞台裏を知らん人の目には、その日の私はさぞええ格好に映ったことでしょう。けど私は、雛人形のように整列して熱唱する同級生の口元を、グランドピアノ越しに、うら寂しい気持ちで眺めていました。
私は、母の勧めで音楽教室に通うことになりました。その甲斐あって、いろんな楽器の腕前はみるみる上がったんですが、肝心の悪声は一向に改善の兆しがありません。それどころか、音楽の授業で私が独唱する番になったら、ここぞとばかりにヤジは飛んで来るわ、やっとのことで絞り出した声は、緊張のあまり裏返って、なおさら笑われるわ…。そんなことが度重なって、とうとう私は、歌というとまるで条件反射のように、蚊の鳴くような、と言うたら蚊に失礼なほど、しょぼくれた声しか出せんようになってしもたんです。
私が受けた心の痛手は思いのほか深く、大人になっても癒えることはありませんでした。そして、もう一生涯、人前で歌うことはないとさえ思うようになりました。
お勤めをして数年目、ピンチが訪れました。会社の宴会で、事情を知らんお得意さんから、よりによって私に歌のリクエスト。一人前の社会人としては断るわけにもいかず、私は決死の覚悟で、若い娘にはそぐわんような懐メロに挑戦しました。そしたら、みんな微笑みながら、私のハスキーな歌声に手拍子を合わせてくれてんよ。「選曲がええ」「音痴やないで」「個性的な声がまた魅力的やなぁ」。(それ、全然ほめてへんのとちゃう?)若干不満の残る(?)評価ばかりでしたが、私は無事1曲を歌い終えただけで十分満足でした。
「みんな楽しそうでよかったな」。放心状態の私に上司がおっしゃいました。「歌やゴルフは人づきあいの潤滑油。決してうまいだけが能やない」。日ごろから完璧主義の傾向が強い私を、やんわり諭す言葉でした。人前で歌えなくなる原因をつくったのは、自分の個性を見失い、無意識のうちに他人と能力を比較していた自分自身やってんね。私は、考え方1つで、欠点もチャームポイントに変えられることに、その時ようやく気づいたんです。
たかが歌、されど歌。自分らしい歌声を探すのにずいぶん歳月を費やしましたが、私に小さな試練を与え、かたくなな心に少しばかりの奥行きをつくってくれた歌というものに、今なお感謝の念を抱かずにはいられません。■
|