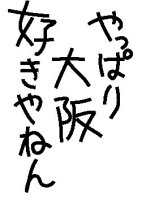|
小学1年生のとき同じクラスになった夕子ちゃんは、透き通るような色白の美人。けど、なぜか全く無表情で、何を話しかけてもウンともスンとも反応のない、謎に満ちた女の子でした。授業中、先生が名前を呼ぼうが、校庭で野球の球が顔をめがけて飛んで来ようが、微動だにしません。にもかかわらず、勉強は体育を除けば常にトップクラス。2年生になっても、謎の美少女の正体はベールに包まれたまま。そのうち、みんな愛想をつかし、夕子ちゃんをまともに相手にする級友は、誰1人おらんようになりました。
そのころ、私は先生から「どんな子とも分け隔てなく遊べる優等生」という、いささか面映い評価をもろててん。そんな使命感と、ある種の好奇心から、私は、地元の商店街でお菓子屋さんを営む夕子ちゃんの家に、思いきって遊びに行ってみることにしました。
ところが驚いたのなんの。店番をしてはるお母さんの傍らで、夕子ちゃんは小さな妹と一緒に、そらぁ楽しそうにはしゃいでてんもん。しかも、私の姿を見つけるや、明るい笑顔で「やぁ、美穂ちゃん、いらっしゃい♪」(え?これが、夕子ちゃんの素顔やのん?)。
夕子ちゃんは、学校ではその後も相変わらず"音無しの構え"を決め込んでいましたが、私にだけはやっとこさ心を開き、やがて、冗談も言い合えるほどの仲良しになりました。夕子ちゃんがいじめられたり、困ってるとき、かばうのはもっぱら私の役目。
「夕子ちゃんは、意思表示が極端に苦手なだけで、ほんまは何でもようできる賢い子ぉや。そやから、あの子のことは私に任せとき」。4年生に進級したころには、私は、自分が夕子ちゃんの唯一の理解者やと自惚れて、すっかり正義の味方の気分になっていました。
そして、4年生の秋。クラス対抗のキックベースボール大会の日のことでした。いつも隅っこで試合を見学してる夕子ちゃんに、一度ぐらい楽しい経験をさせたいと思い、私は、ためらう彼女を無理やり運動場に引っ張り出しました。けど、夕子ちゃんは、攻撃でも守備でも、ただただ突っ立ったまま。私らのクラスは大敗を喫してしもたんです。
激怒した級友たちは、一斉に夕子ちゃんを取り囲みました。普段なら、ここで私が助け舟を出したでしょう。けど、みんなの非難を一身に浴びても依然、表情ひとつ変わらん夕子ちゃんを見てるうち、ふと魔が差したんか、私の中に蓄積されてきたイライラが一気に噴出してしもたんです。
「あんたのためを思う気持ちが、なんでわかれへんのん!」。
突然、夕子ちゃんは顔をゆがめて号泣しました。彼女がみんなの前で感情を表わすのは、あとにも先にもこれが初めてでした。親切心から出た私のお節介を断るに断れず、必死の思いで運動場に立ってたんやろね。そんな苦しい心の内が配慮できなかったことに、ようやく気づいても後の祭り。翌日から、夕子ちゃんはプッツリと学校に来なくなりました。
数日後、心配になって様子を見に行くと、夕子ちゃん一家はお菓子屋さんごと、もぬけの殻でした。あれから何十年…。夕子ちゃんの家があった場所には大きなマンションが建ち、町の様子もすっかり変わってしまいました。今はただ、夕子ちゃんが、どこか遠くの町で元気に暮らし、ええお母さんになっててくれたらなぁと願うしかありません。
あのときは、ごめんやで、夕子ちゃん…。■
|