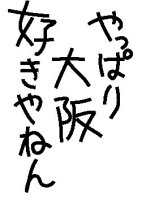|
「美穂もいっぺん、おじいちゃんのとこ行ってみるか」。次の日曜日、父は私を初めて祖父の見舞いに連れて行ってくれました。「面会謝絶」の札がかかった扉を開けると、病室には、それまで嗅いだことのない異臭が充満していました。そして、いくつもの点滴や管に繋がれてベッドに横たわっていたのは、骸骨と見まがうほどに痩せこけ、そやのに下腹のあたりだけが異様にふくれあがった祖父でした。「え…これが、私のおじいちゃん…?」
祖父はわずかに唇を動かしたように見えましたが、次の瞬間、まぶたを半分開けたまま、すうっと眠りに就きました。もはや鎮痛剤も効き目がなくなった祖父の意識は混濁し、悪魔が枕元でにらんでいるとか、戦死した息子が呼びに来たとか、恐ろしげなうわごとを繰り返していました。祖父の身に、もうすぐ何が起ころうとしているのかを本能的に察知した私は、名状しがたい恐怖に身震いし、祖父の顔をまともに見ることすらできませんでした。
それから数日後、病院に詰めていた父から、深夜に電話がありました。「おじいちゃんが、たった今、亡くなった」。生まれて初めて経験する肉親の最期でした。私は、なんとも曖昧な喪失感と、やっと両親が自分のところに戻ってきてくれるという安堵の気持ちが交錯する、複雑な心理状態を自覚していました。
根っからの商売好きで、ユーモアがあって、私を「小山家の清少納言」と呼んで、ことのほか可愛がってくれる祖父を、私は心から尊敬していました。にもかかわらず、ちょっと家事が億劫になったというだけで、たとえ一瞬でも、祖父の早い死を望むような思いが頭をかすめたり、臨終に際しては、悲しみより、むしろ安心感を抱いてしもた自分の冷酷さを、私は誰にも打ち明けることができませんでした。
その後、数か月にわたる睡眠不足と疲労の蓄積がたたったのか、父は肝臓を患い、母は一時的にではありましたが、視力をほとんど失いました。祖父は入院中、息子のお嫁さんの中で一番お気に入りの母に頼りきりで、ほかの誰が世話をしても嫌がったんやと、そのとき初めて父から聞かされました。母が一日も病院通いを欠かせへんかったのは、それが大きな理由でした。
当然、お医者さんも看護師さんも、大事なことは真っ先に母に話すようになります。そうなると、面白ぅないのは父の兄やお嫁さん。母の一挙手一投足に難癖をつけては、露骨にいじめることも2度や3度ではなかったようです。家に残した子どもは心配やわ、周囲にはよけいな気を遣わなあかんわ、まさに針のむしろに座りながらの看病。そんな母の苦境も知らず、祖父の入院で自分だけが犠牲になっていると思い込んでいた身勝手さを痛感し、私はさらに自責の念を募らせました。それからというもの、母が留守のときの、手軽で贅沢なご馳走やったおすしは、どうしても私ののどを通らんようになってしもたんです。
市場の例のおすし屋さんは、その後も、私が通りかかると「あんた、大きなったなぁ。元気にしてるか?」と、親しそうに声をかけてくれましたが、祖父の死にまつわる出来事の記憶が呼び起こされるのがつらくて、私は一度も笑顔を返すことはできんままでした。
それからいくつ年月を重ねたでしょうか。各界の著名人が贔屓(ひいき)にし、一流の職人さんが何人も輩出したそのおすし屋さんも、時代の流れには逆らえず、昨年の春、永年続いた暖簾(のれん)を下ろしました。
幼い日に犯した心の罪を悔いる私に、時効を告げるかのように。
|