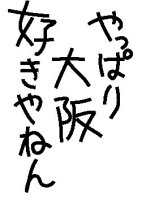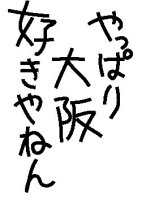|
物心ついた頃からの、母のスパルタ教育のおかげでしょうか。私は、食べ物の好き嫌いは一切ありません…と言いたいとこやけど、実は、ひとつだけどうしても苦手なものがあるんです。それは、話せば長いことながら…。
小学2年生になって間もない頃、父方の祖父が体調を崩して緊急入院。検査の結果、もはや治癒の見込みがないほど、病状が悪化していたことがわかりました。その日から、両親と、おじ・おばたちが交代で祖父の付き添いをすることになり、中でも責任感の強い母は、家事もそこそこに、ほぼ連日、昼間から深夜まで病院に詰めて、献身的に看病に専念しました。そのため、私ら3人のきょうだいは、母が留守の間、当番制で炊事をすることにしたんですが、上の兄は高校受験を控えてた上に、ともかく不器用(!)。次兄は、自分の番になると、なんやかやと理由をつけては、姿をくらましてしまいます。結局、末っ子の私が食事の仕度を一手に引き受けざるを得なくなりました。
今なら、コンビニのお弁当や即席の食品が豊富やから、大して不自由もないでしょうが、当時はそう簡単にはいきませんでした。私は、自宅近くの、今も全国に名の知れた黒門市場で、いっちょ前に、材料を仕入れることから始めなあかんかったんです。それでも、初めのうちは、コロッケやてんぷら、ハムやかまぼこ、コンビーフの缶詰やメザシなどで何とか凌げたんですが、そんな出来合いのメニューだけでは、すぐに飽きが来てしまいます。
けど、唯一のレパートリーやったカレーひとつつくるにも、ジャガイモやニンジンがいくついるのか、どんな肉を何グラム買うたらええのか、全く見当もつきません。ある時は材料を買い過ぎて腐らせたり、買物中に所持金が足らんようになったり、やっとこさ料理ができても、ごはんの水加減を間違えておかゆになったり、毎日がスカタンの連続でした。
夜遅く帰宅する母を待ち構えて相談しようにも、看病疲れで精根尽き果て、何を聞いても上の空。あるとき、諦め切れずについ愚痴を言うと、母は「もう、鬱陶しい話はせんといて!」と声を荒げたばかりか、炊事場の後片付けがおろそかやと、私をヒステリックに叱りつけました。いつも優しく冷静で、完全無欠やと信じていた母から生まれて初めて感情をぶつけられたショックで、私は夜通し涙が止まりませんでした。
そんなある日、重い買い物かごをさげて、重い足取りで市場を歩いていた私の目に飛び込んできたのは、有名な老舗のおすし屋さんの陳列でした。「わぁ、きれい。これやったら簡単で美味しいし、栄養もある。けど、こんなん買うて食べるて、贅沢過ぎるかなぁ…」。けどその夜、私は母の明快な返事に救われた思いがしました。「少々お金は使ぅてもええから、しっかり栄養のあるもん食べて、おじいちゃんが良うなるまで我慢してや」。
それからというもの、献立に行き詰ったときはいつも、おすし。ところが、それが一週間ほど続いたある日、お店のおっちゃんが私の顔をのぞき込んで、いかにも気の毒そうに言いはりました。「あんたのお母ちゃん、ごはんつくってくれへんのか。おっちゃんが、お菓子をオマケにあげるさかい、がんばりや」。他人さまから同情されたことで、小さなプライドがいたく傷つき、それまで私の心の奥深く抑え込んでいたある思いが、一気に噴出しました。
「おじいちゃんなんか、早よ死んでしもたらええのに!」
|