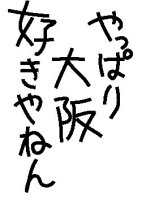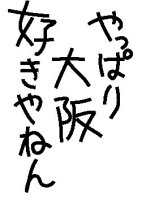|
同級生のハジメ君は、中学2年生やというのに相撲の新弟子ほどの大柄で、学生服の前をはだけ、眉を剃りこんだ威圧的な風体。なんでも、夜な夜な良からぬ仲間とつきおうてるというのが、専らの噂でした。
「ハジメのお父ちゃんの仕事、銀行強盗やねんてぇ! 50回も事件を起こして、もう一生、刑務所から出られへんて、私のお母ちゃんが言うてたで!」。誰もがハジメ君を避けるようになったんは、マリちゃんのこの一言がきっかけでした。
それからというもの、授業妨害はするわ、大声で悪態をつくわ、ハジメ君の乱行はエスカレートするばかり。けど、別に女の子に暴力を振るうたり、飲酒や喫煙をするわけではありません。それどころか、家ではこっそりメダカを飼育してたり、ピラミッド型の紙の容器に入った甘いコーヒー牛乳が大好物やったり、案外かわいらしいとこもあってんよ。私は、ハジメ君の不敵な面構えの奥に、ある種の哀愁とデリカシーを感じ取っていました。
ある日、ハジメ君が運動場の片隅で、クラスで一番小さな男の子に、何やらイケズを言うて泣かせている現場に出くわしました。けど、みんな仕返しが怖ぁて、見て見ぬ振りで通り過ぎていきます。業を煮やした私は、身の危険も顧みず大声で注意しました。
「大きな図体して、弱い者いじめは卑怯やないの」「じゃかっしい。オバはんは黙っとれ!」「黙るかい、このオッサン!」。こうなったら、もう売り言葉に買い言葉。「生意気な女やのぉ。コーヒー牛乳ぶつけたろか」「へへん、ぶつけられるもんやったら、ぶつけてみい!」。
ブシュッ…鈍い破裂音とともに右の肩に軽い衝撃が走ったと思ぅたら、私の全身は見事、コーヒー牛乳色に染まっていました。髪の毛や制服のスカートから、やや粘り気のある液体をポタポタ滴らせ、身動きもでけへん私。ハジメ君もまた、好物の飲料が想像を絶する攻撃力のある凶器となったことに仰天し、その場にポカンと立ち尽くしていました。
保健室に連れて行かれた私は、ショックで足がガタガタ震えてはいたものの、幸い掠り傷一つなく、お湯で頭と顔を洗い、体操服に着替えた頃には、すっかり落ち着きを取り戻していました。私らが呼ばれた校長室の前は黒山の人だかり。そして、担任の先生が2人に事情を聞こうとした途端、ワッと泣き出したのは、私ではなく、ハジメ君の方でした。
「小山のこと、ちょっと驚かせたろと思ただけやのに、えらいことになった。ごめんな?」。ハジメ君はワァワァ泣きながら、同級生から疎まれて寂しかったこと、ほんまはみんなと仲良うしたかったことなど、それまでの秘めたる胸の内を、堰を切ったように吐露し始めました。廊下に集まった同級生は、思わぬ展開をただ息をのんで見守るばかりでした。
その時わかったことですが、ハジメ君のお父さんはれっきとしたサラリーマン。少々気が荒いため、酔うた勢いも手伝うて、夜の道頓堀で同僚と口論しているのを同級生のお母さんが目撃し、尾ひれをつけて話したのが、あらぬ噂に発展したというのが事の真相でした。大人の不用意な一言が、1人の少年の心を歪めてしまうこともあるんですね。ハジメ君の攻撃的な態度は、誰かに救いを求める気持ちの裏返しやったのかもしれません。
晴れて誤解の解けたハジメ君は、私への刃傷沙汰(?)をいたく反省したのか、以来、ちょっと照れ屋で繊細なフェミニストぶりを、包み隠さず発揮するようになりました。そして、学校一のワルを号泣させた上、彼が"よい子"に大変身するきっかけを、身を挺してつくった私が、栄えある"鉄の女"の称号を与えられたのも、その日からでした。
|